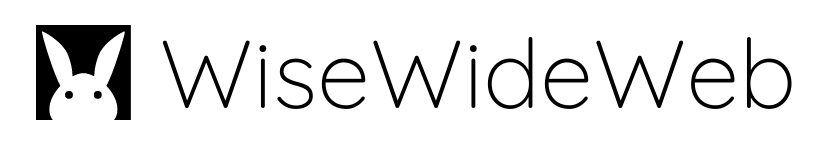記事内に広告が含まれていることがあります
健康保険の扶養家族は、通常何人扶養にしても保険料が上昇することはありません。
しかし、例外もあり、
- 健康保険加入者本人の年齢(39歳以下 or 65歳以上)
- 被扶養者の年齢(40歳~64歳)
- 加入している健康保険組合の規約
この3つの状況により、扶養家族の影響で保険料が上がる可能性があります。
正確には、介護保険料分が発生するということになるのですが、一体どんな制度なのでしょうか?

みてみましょ!
はじめに:介護保険料の対象者
まずはじめに、介護保険料のことを簡単に説明します。
介護保険料は、40歳以上の人が負担しますが
- 40歳から64歳以下の人
- 65歳以上の人
が介護保険法で、分けられています。
40歳から64歳以下の人は「介護保険第二号被保険者」と呼ばれ、介護保険料は加入している健康保険料と一緒に請求されます。
65歳以上の人は「介護保険第一号被保険者」と呼ばれ、介護保険料はお住まいの自治体から請求されます。
特定被保険者制度
以上のような介護保険料がかかる年齢や、かかり方を前提にすると

じゃあ、健康保険の加入者が35歳で扶養家族が42歳だった場合、介護保険料はかかるの?かからないの?
という疑問がうかびます。
その答えが、健康保険法に以下のように書かれています。
健康保険法 附則
(特定被保険者)第七条 健康保険組合は、第百五十六条第一項第二号及び第百五十七条第二項の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、介護保険第二号被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第二号被保険者である被扶養者があるものに限る。以下この条及び次条において「特定被保険者」という。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができる。
簡単にいうと、
「健保組合が規約で定めれば、扶養家族が40~64歳以下の年齢の時に39歳以下とか65歳以上の加入者に介護保険料を請求していいよ!で、請求される加入者のことは”特定被保険者”って呼ぶことにする(キリッ)」
ということになっていて、健保組合次第で加入者本人が対象外でも、扶養家族分の介護保険料がかかる可能性があります。
特定被保険者を規約で定めている健保組合の場合、特定被保険者となりうるのは次の2パターンになります。
パターン1:加入者本人が39歳以下、被扶養者が40~64歳以下だった場合
本人はまだ介護保険料がかからない年齢でも、扶養家族が介護保険2号被保険者だと、家族分の介護保険料がかかってしまいます。
- 例)夫(38歳)が加入者、妻(41歳)が扶養家族
- 例)子(29歳)が加入者、親(63歳)が扶養家族
パターン2:加入者本人が65歳以上、被扶養者が40~64歳以下だった場合
本人が65歳以上で、扶養家族が介護保険2号被保険者でも、家族分の介護保険料がかかってしまいます。
- 例)夫(68歳)が加入者、妻(63歳)が扶養家族
- 例)親(66歳)が加入者、子(43歳)が扶養家族

65歳以上の人は介護保険料がもともとかかっているのでは?
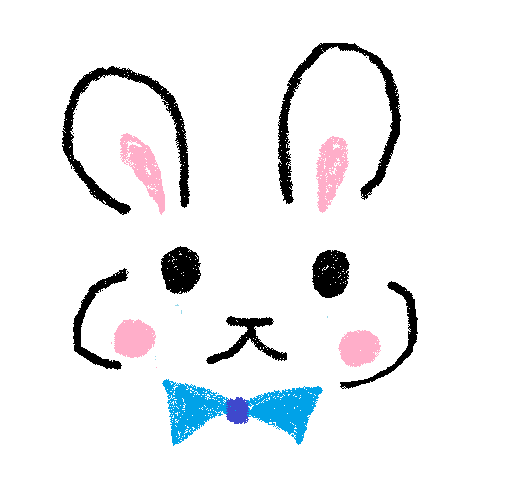
65歳以上は介護保険第一号被保険者で、介護保険料は会社でなく自治体から請求されているんだよ。だからこのパターンの場合、本人の介護保険料は自治体から請求。家族の介護保険料を健保から請求ということになるね(長ゼリフ)
特定被保険者を規定している健保は?
では、どこの健康保険組合がこの特定被保険者制度を規約に定めているのでしょうか?
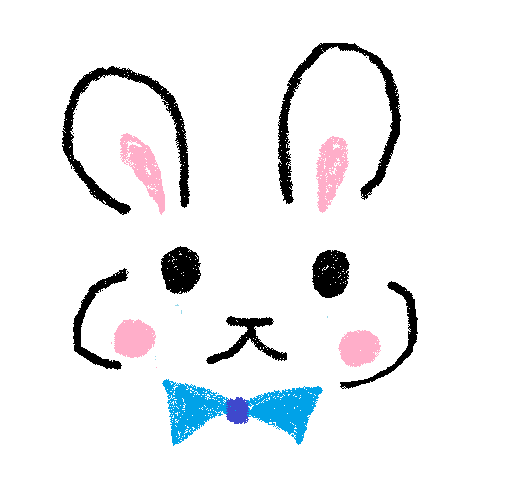
すみません!
全部はわかりません!
ただし、半数近くの方が加入している「全国健康保険協会(協会けんぽ)」は、規約に定めていませんので、扶養家族の介護保険料が発生することはありません。
協会けんぽ以外の健保組合の方は、お手数ですが個別で健保組合へお問い合わせください。
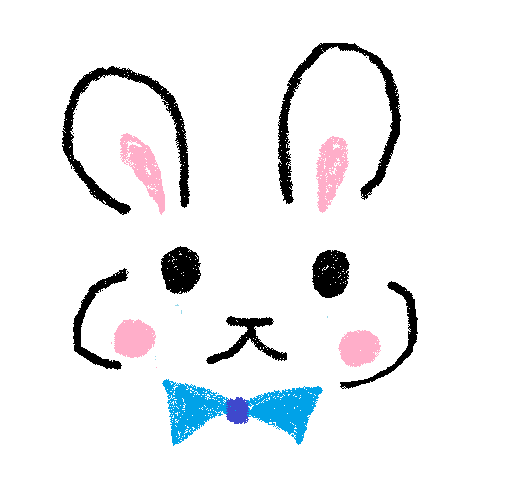
「〇〇健保 特定被保険者」で検索すればヒットするかもしれませんね!
特定被保険者制度の意義は?
特定被保険者の方にとっては、
「規約のない健保なら介護保険料かからないのに!」
と、くやしい思いをされることとは思うのですが制度の意義もありますので少しだけ。
健保組合は、扶養家族も含めた40歳~64歳までの加入者分の介護保険料を国に納めなければなりません。
そして、特定被保険者制度を規定してもしなくても納める額は変わりません。
よって、特定被保険者制度を規定していない健保組合の場合、40歳から64歳の加入者が「扶養家族だけ40歳から64歳の世帯」の介護保険料も負担していることになってしまいます。
これは公平でないということで、負担の偏りを避けるために規約で可能とされているのが特定被保険者制度というわけです。
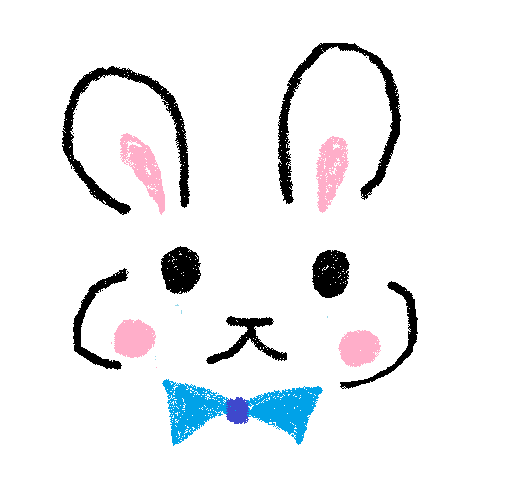
だったら、特定被保険者を強制にすればいいじゃんよ!とは思ってしまいますが…
おわりに
以上、健康保険の特定被保険者の制度について説明しました。

あれ、なんでわたし29歳なのに介護保険料がかかってんの!?
という方はこの制度が理由かもしれませんし
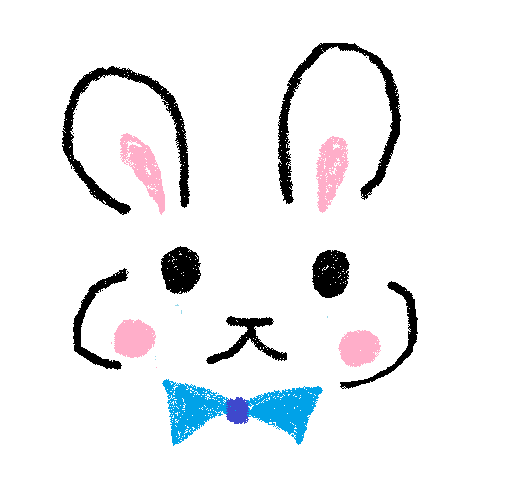
国民健康保険の家族を社保の扶養にいれて保険料負担を抑えよう!
と考えている人は、思いがけぬ介護保険料が発生し皮算用が狂ってしまわぬよう、本当にお得になるか調べてみてもよいかと思います。
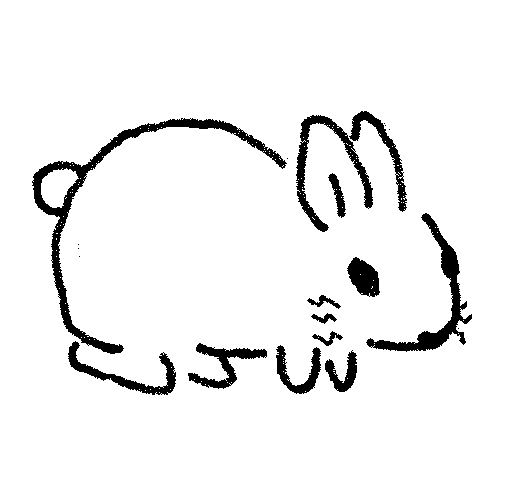
おっしまい( ´∀`)